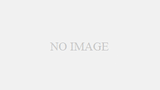日本のスタバは、なぜ「絶好調」なのか 米国本社が不調なのに、成長を続けられているワケ
日本全国どこへ行ってもほぼ満席の状態が続き、季節ごとの限定フラペチーノが発売されるたびにSNSが盛り上がるスターバックス。日本では着実に店舗数を拡大し、業績も絶好調を続けています。一方で、本国アメリカのスターバックス本社は苦戦を強いられ、人員削減やメニュー簡素化などの対策を進めています。なぜ日本のスタバだけが好調なのか、その秘密を探ってみました。
数字で見る日本スタバの「絶好調」ぶり
日本のスターバックスの売上高は、2023年比で111.1%、2019年比では159.9%という驚異的な成長を遂げています。営業利益も2023年比で115.4%、純利益は122.5%と2ケタの増収増益を記録しており、まさに絶好調と言える状況です。
特筆すべきは店舗生産性の高さです。スターバックスの国内店舗数は2023年比で105.4%の増加ですが、売上高は111.1%と店舗数の増加率を上回っています。これは、単に店舗数を増やして売り上げを伸ばしているわけではなく、1店舗あたりの売上高(1億6200万円)も着実に増加していることを示しています。
日本のスターバックスは、全世界にある店舗の4.9%を占めるにすぎませんが、売上構成比では5.9%を占めており、店舗あたりの売上貢献度が高いことがわかります。
米国本社が直面する苦境
一方、米国のスターバックスは業績不振に直面しています。2024年2月には1100人の人員削減を発表し、採用予定だった数百のポジションも停止するなど、経営立て直しの途上にあります。
また、メニューの簡素化も進めており、売れ行きが悪いドリンクをメニューから外すなど、顧客の待ち時間を減らして効率化を図る取り組みも行っています。
スターバックス全社の2024年9月期の売上高は前年度比で100.6%とわずかな伸びにとどまり、営業利益は8%弱の減少、純利益も8.8%減と厳しい状況です。この不調の主な原因は、売上の7割以上を占める北米エリアの伸び悩みと、中国市場の消費減退によるものとされています。
日本スタバの強み①:日本独自の商品開発力
日本のスターバックスが好調の最大の理由の一つは、日本独自の商品開発力です。季節限定の商品開発や地域ごとの「ご当地メニュー」開発は、日本のスタバの特徴となっています。
例えば、2025年春の限定商品「春空 ミルクコーヒー フラペチーノ」は、フラペチーノに入っているいちごのボールを割って味変を楽しめる商品で、700円超という価格にもかかわらず、各店で人気となっています。こうした季節限定フラペチーノは月に1〜2回のペースで発売され、SNS上の話題を生み出し、売上につなげています。
また、2020年から始めた日本独自のティー専門店「スターバックス ティー & カフェ」も人気を博しており、コーヒーと紅茶の両方を楽しめる「二刀流」のコンセプトで、すでに15店舗まで拡大しています。
米国本社が管理するのはミッションなどのブランド方針、コーヒー豆の生産、使用するコーヒーマシンのみで、フラペチーノなどの新商品開発や接客、店づくりはすべて日本法人が独自に決定できる裁量を持っています。この自由度が、日本市場に適した商品展開を可能にしているのです。
日本スタバの強み②:立地・客層に合わせた店舗開発力
日本のスターバックスのもう一つの強みは、立地や客層に合わせた特色ある店舗開発です。富山県の「世界一美しいスタバ(富山環水公園店)」は訪日外国人にも人気の観光スポットとなっています。
また、渋谷のスクランブル交差点に面したSHIBUYA TSUTAYA 2F店は、窓から交差点を見下ろせるというクチコミが広がり、外国人観光客のメッカになっています。
さらに、子連れ向けに設計された越谷イオンレイクタウン mori 3階店では、子ども向けメニューの用意や、ベビーカーでも利用しやすい店内設計など、きめ細かな配慮がなされています。
日本のスタバは社内に店舗設計部門を持ち、一級建築士の資格を持つスタッフを複数抱えているため、立地や客層に合わせた最適な店舗開発が可能となっています。こうした各地域の特性を活かした店舗づくりが、顧客の満足度向上とリピート率の向上に寄与しているのです。
日本スタバの強み③:デジタル化によるCX戦略
日本のスターバックスは近年、デジタル化にも積極的に取り組んでいます。2016年に公式モバイルアプリを導入し、2020年には「モバイルオーダー&ペイ」を全店舗で導入しました。
このサービスは当初、2019年6月に都内56店舗でスタートしましたが、コロナ禍を契機に全店舗への展開が加速し、現在では定番サービスとして定着しています。全国どの店舗でも、店頭で待つことなく商品をテイクアウトできる利便性が高く評価されています。
アプリでは購入金額に応じてポイントがたまる「スターバックス リワード」プログラムも展開し、固定客化を図っています。さらに2024年5月からは、会員登録なしでもモバイルオーダーを利用できる「App Clip」サービスも導入し、新規客開拓にも力を入れています。
日本スタバの強み④:ミッションへの忠実さと独立性
スターバックスの強さの根底には「ミッション」があります。「一杯のコーヒー(ティー)で」「一人一人のお客様に対して、マニュアルのない、寄り添ったサービスをする」「一つ一つのコミュニティに対して、違う店を作っていく」という理念を追求し続けています。
日本のスターバックスは、このミッションに忠実でありながらも、2015年にTOBによって米国本社の完全子会社となり上場廃止したことで、より自由に成長戦略を展開できるようになりました。皮肉にも、米国本社の子会社になったことが、日本のスターバックスがより自律的に成長できる要因になったのです。
米国スターバックスは2024年に新CEOが就任するなど経営体制の変革を進めていますが、日本法人はその影響をさほど受けることなく、日本市場に適した独自の戦略を進めることができています。
日本スタバから学ぶ、グローカル経営の成功法則
日本のスターバックスの成功は、グローバルブランドの強みを活かしながらも、ローカル市場に適応する「グローカル」戦略の成功事例と言えるでしょう。米国スターバックスの幹部も、日本は重要なマーケットであり、大きな成長可能性を秘めていると評価しています。
「日本は重要なマーケットで、本社にとっても日本における将来のチャンスは大きいとみている」と米スタバ幹部は語っています。進出から20年以上経った今でも、スターバックスは日本においてまだ成長の余地があると考えられています。
米国本社が苦戦する中でも日本のスターバックスが好調を維持できているのは、グローバルブランドの価値を維持しながらも、日本市場に合わせた独自の戦略を展開できる自由度と、それを可能にする経営体制があるからこそ。今後も、季節ごとの新商品や特色ある店舗展開で、日本のカフェ市場をリードし続けることでしょう。
結論:独自性と適応力が生み出す持続的成長
日本のスターバックスが米国本社の不調にもかかわらず絶好調を維持している秘訣は、日本独自の商品開発力、立地に合わせた店舗展開、デジタル化によるCX戦略の強化、そして経営の独立性にあります。
グローバル企業でありながら、日本の文化や消費者の嗜好に深く根ざした戦略を展開する柔軟性が、日本でのスターバックスの持続的な成長を支えています。日本法人が持つ大きな裁量と独自性こそが、世界的に見ても特異な成功パターンを生み出しているのです。
カフェチェーンとしては国内最多の店舗数を誇り、今後も拡大を続ける日本のスターバックス。その成功モデルは、日本市場に参入を目指す他のグローバル企業にとっても大いに参考になるでしょう。