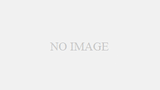いま、建築界のみならず一般メディアやSNSでも大きな話題となっているのが、世界的建築家・隈研吾氏が手がけた公共施設の「腐朽」問題です。美しい木材を大胆に使ったデザインが称賛を浴びたはずの建物が、わずか数年~20年足らずでカビや腐食に悩まされている現実。そこには、建築の理想と現実が交錯する、知られざるエピソードや業界の裏話が詰まっています。
「腐る建築」衝撃の現場
2024年秋、群馬県富岡市役所の外装木材がわずか6年で腐り始めているとの指摘がSNSで拡散され、全国の隈研吾作品に同様の現象が相次いで報告される事態に発展しました。さらに栃木県那珂川町の「馬頭広重美術館」では、開館から24年で木製ルーバーなどの老朽化が進み、改修費が3億円にも上るためクラウドファンディングが立ち上がるほどの騒ぎに。
「腐る建築」という言葉自体が、鉄やコンクリートの「不朽」のイメージと真逆で、多くの人に衝撃を与えました。実際、屋根や壁の木材が崩れ落ちる様子は、まるで廃村の廃屋のようだったと報じられています。
なぜこんな事態に?――建築家も承知のリスク
この現象の根本には、隈研吾氏の「木を大胆に外装に使う」デザイン哲学があります。美術館や市役所など、公共建築の顔となる部分に木材を多用し、自然との調和や日本的な美意識を現代建築に持ち込もうとしたのです。
しかし、専門家によれば「木材そのものが悪いのではなく、使い方に問題があった」との指摘が多数。日本の伝統建築では、木は庇の下など風雨に晒されない場所や、水に強い樹種を選んで使うのが常識。しかし隈氏の建築では、外装に合板やベニヤなど水に弱い木材を無塗装で使うことが多く、さらに予算や施工の都合で防水処理が十分でなかったケースもあったと言われています。
実は、隈氏自身も「木を屋根の上に置いたら腐るのではないか」という疑問を設計当初から認識していたと、講演会で語っていた記録も残っています。それでも「白木の美しさ」や「写真映え」を優先し、リスクを承知でデザインを貫いた――ここに建築家としてのジレンマと、現実とのギャップがあったのです。
「写真映え」と「フィクション」――建築業界の裏側
建築エコノミストの森山高至氏は、「建築は写真で流通する」「作品はフィクションである」という隈氏の姿勢を指摘しています。つまり、完成直後の美しい姿がメディアやSNSで拡散されることで、建築家の評価や次の仕事につながる――そのため、長期的な耐久性よりも短期的な見映えが重視される傾向が強まっていたというのです。
この「作品はフィクション」論は、建築業界でも賛否両論。あるベテラン建築家は「本来、木造建築は維持管理を前提とした文化がある。クライアント(発注者)に十分な説明がなされていないのでは」と疑問を呈しています。
「木の匠」か「木のデコレーション」か――現場の本音
隈研吾氏は「木の匠」と呼ばれる一方で、実際の現場では「木を表面に貼るだけのデコレーション」と揶揄されることも。中にはアルミに木目をプリントしただけのパネルを使う例もあり、「本物の木の建築」とは言い難いとの声もあります。
また、「木材の腐朽は建物の耐久性には影響しない、あくまで装飾」との説明もありますが、税金を使った公共施設で短期間に外観が劣化することへの市民の不信感は根強いものがあります。
「クラウドファンディングで改修」――新しい公共建築の課題
馬頭広重美術館では、改修費用3億円のうち1000万円をクラウドファンディングで集めるという異例の対応が話題に。これには「美しい建築を維持するために市民も負担を」という新しい公共建築のあり方を問う声も上がっています。
隈研吾氏のコメントと今後
隈氏は「保護塗料の性能が低かった」と説明していますが、業界内では「そもそもそのリスクは承知していたはず」と冷ややかな見方も。今後は、まだ実験段階の新素材や工法を公共施設に採用する際の説明責任や、建築家倫理の問題に発展する可能性も指摘されています。
まとめ――美しさと持続可能性のはざまで
隈研吾建築の「腐る」問題は、単なる設計ミスや素材選びの失敗ではなく、「美しさ」と「持続可能性」、「写真映え」と「現実」の間で揺れる現代建築の象徴的な事件です。自然素材を生かしたデザインがもたらす感動と、その裏に潜む維持管理の難しさ――この両立こそが、今後の建築界に問われる最大の課題なのかもしれません。
最後に、SNSでは「腐っても隈研吾」「次はどんな木の使い方を見せてくれるのか」と、皮肉交じりの期待も。建築の未来を考えるきっかけとして、この「腐る建築」騒動を見つめ直してみてはいかがでしょうか。