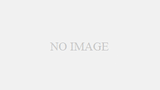コロナ禍を経た現在、結婚式の形が大きく変わりつつあります。「ジミ婚」「ナシ婚」という言葉をよく耳にするようになりましたが、これらの新しい結婚スタイルがブライダル産業に与える影響は想像以上に深刻です。業界関係者の声や実際の現場エピソードを交えながら、結婚式の「今」と「これから」について探っていきましょう。
- ジミ婚・ナシ婚とは?増え続ける新しい結婚スタイル
- 深刻化するブライダル業界の危機 ‐ 3割が赤字の現実
- 1. 「ナシ婚」「ジミ婚」の拡大
- 2. 物価高騰による影響
- 3. 競争激化と経営難
- 4. 婚姻数の減少
- 相次ぐ結婚式場の倒産 ‐ 現場からの悲鳴
- リアルな現場エピソード ‐ ジミ婚をめぐる裏話
- 地味婚に対する周囲の反応
- ウェディングプランナーが明かす困った花嫁行動
- 衝撃のプランナー行動
- セレブたちのジミ婚から学ぶ「おしゃれな地味婚」
- ブライダル業界の生き残り策 ‐ 変化への対応
- 1. 差別化戦略の重要性
- 2. サービスの多様化
- 3. 顧客満足度の向上
- 日本のカップルの実態 ‐ 出会いから結婚まで
- 今後の展望 ‐ ブライダル産業の行方
- まとめ ‐ 変わりゆく結婚式の形
ジミ婚・ナシ婚とは?増え続ける新しい結婚スタイル
「地味婚」とは、結婚式の内容を簡略化し、前後に行うイベントを省略するスタイルのことです。披露宴の演出を控えめにしたり、親しい家族や友人のみで小規模な食事会を行ったり、挙式だけにとどめたりと、その形はさまざまです。一方「ナシ婚」は、挙式・披露宴自体を行わず、入籍のみで結婚を済ませる形式です。
このようなスタイルが選ばれる理由としては、「結婚式より新生活にお金を使いたい」「準備が大変な披露宴を避けたい」「派手なセレモニーに興味がない」「主役として目立つことが苦手」などが挙げられます。また、妊娠中であることや再婚・高齢婚の場合に選ばれることも多いようです。
実際、結婚式の形は時代とともに変化してきました。バブル期には高級ホテルでゴンドラに乗って新郎新婦が登場するような「派手婚」が主流でしたが、バブル崩壊後の1990年代に「地味婚」が広がり始めました。2000年代にはゲストハウスでのウェディングが流行し、2010年代には東日本大震災の影響もあり、人との「繋がり」を重視する傾向が強まりました。
深刻化するブライダル業界の危機 ‐ 3割が赤字の現実
結婚式場業界は現在、非常に厳しい局面を迎えています。帝国データバンクの調査によると、2023年度における結婚式場運営企業のうち35.6%が赤字となり、「減益」を含めると業績悪化は全体の約6割に達しています。2024年度の市場規模は4800億円前後と見込まれるものの、2018年度(6163億円)と比較すると約8割の水準にとどまり、コロナ前の水準には完全に戻っていない状況です。
この業績悪化には主に4つの要因があります。
1. 「ナシ婚」「ジミ婚」の拡大
コロナ禍を機に、小規模な結婚式や結婚式自体を挙げない選択をするカップルが増加し、従来の豪華な披露宴を伴う結婚式が敬遠される傾向が強まっています。
2. 物価高騰による影響
人件費、食材費、光熱費などのコストが増加しているにもかかわらず、式場側は価格の大幅な引き上げが難しい状況に置かれています。コース料理の料金を引き上げた式場もありますが、利用者の負担を考慮し、十分な価格改定ができない企業が多いのが現状です。
3. 競争激化と経営難
全国各地に結婚式場が乱立して集客競争が激化し、式場ごとの価格競争が進んで利益率が低下しています。これに伴い、ブライダル関連業者の倒産も増えており、式場の経営はますます厳しくなっています。
4. 婚姻数の減少
日本の婚姻数は長期的に減少傾向にあり、2023年の婚姻件数は約49万組で、前年比で約5万組減少しました。これは1990年代の年間80万組以上と比べると大幅な減少です。少子化や非婚化の影響により、この傾向は今後も続くと見られています。
相次ぐ結婚式場の倒産 ‐ 現場からの悲鳴
業績悪化を受け、結婚式場の倒産が相次いでいます。2024年2月には福岡県の大手結婚式場「アルカディア」が破産を申請し、業界に衝撃が走りました。1973年創業の老舗でしたが、コロナ禍による業績悪化などが原因で、負債総額は約40億円に上りました。この倒産により、式場で挙式予定だった多くのカップルが影響を受けています。
また、広島の結婚式場「シャイン」も2023年8月に破産を申請しており、負債総額は20億円に達しています。コロナ禍で急減した挙式数が回復せず、経営を維持することが困難になった典型的な例です。
ブライダル産業で倒産や廃業が目立つ状況は続いており、2024年度の倒産(負債1,000万円以上)は13件(前年度比27.7%減)で、過去10年で2023年度の18件に次ぐ2番目の高水準となっています。
リアルな現場エピソード ‐ ジミ婚をめぐる裏話
地味婚に対する周囲の反応
地味婚を選んだカップルが周囲から受ける反応は様々です。ある女性は、家族と親しい友人だけを招待して小規模な結婚式を行ったところ、招待した友人から「正直、地味だったよね〜。私が結婚するなら絶対、もっと大勢の人を呼んで、高級ホテルとかでやりたい」と言われてしまいました。実はその女性は夫と海外ウェディングも計画していましたが、失礼な発言をした友人には敢えて報告せず、距離を置くことにしたそうです。
このエピソードからも分かるように、地味婚を選んだことでの周囲の反応に傷つくカップルは少なくありません。自分たちの考えで選んだ結婚式のスタイルを尊重してもらえないことは、当事者にとって大きな心の傷となります。
ウェディングプランナーが明かす困った花嫁行動
ウェディングプランナー歴約5年、計600組以上の結婚式をサポートしてきたプランナーが明かす「花嫁さんのちょっと困った行動」には、以下のようなものがあります:
- 打ち合わせのたびに値下げ交渉をする
- 花嫁同士の情報交換で「○○さんはやってもらってた」と比較する
- SNSで「節約術」「交渉術」「プランナー名」を公開する
- 指示書の内容が細かすぎる一方で、イメージが曖昧すぎることもある
- お願いしたことをやってこない、期限を守らない
- 返信が遅いのに自分への返信は即レスを求める
こうした行動は、相互理解と信頼関係を築くべき花嫁とプランナーの関係に亀裂を生じさせる原因となっています。
衝撃のプランナー行動
一方で、プランナー側のモラルに問題があるケースも報告されています。あるカップルの場合、担当プランナーが新郎に対してアタックするような行動を取り、新婦に冷たい態度を見せていたといいます。新郎のことは名前で呼ぶのに、新婦のことは「新婦さん」と呼んだり、打ち合わせ以外でも新郎に頻繁に電話やメールをしたりと、明らかに不適切な行動が見られました。
このケースでは、最終的にプランナーから「彼と別れてほしい」という驚きの電話まであり、「あなたのワガママにうんざりしている」など新婦に対して心無い言葉を投げかけたそうです。このような極端なケースは稀かもしれませんが、結婚式という人生の大切な瞬間を準備する過程で、当事者が不快な思いをするケースがあることは事実です。
セレブたちのジミ婚から学ぶ「おしゃれな地味婚」
地味婚はネガティブなイメージで語られることも多いですが、海外セレブの中には地味婚をおしゃれに取り入れている人も少なくありません。
スーパーモデルのエミリー・ラタコウスキーは、交際わずか2週間ほどで、ニューヨークの市庁舎で結婚式を挙げました。この際、花嫁はマスタード色のパンツスーツ(ZARAの商品で約23,000円)を選び、伝統的な純白のウェディングドレスではなく、個性的でおしゃれな装いで注目を集めました。
また、ファッションアイコンのオリヴィア・パレルモは、ベッドフォードにある市庁舎の庭で家族と数名の友人のみを招待した小規模な結婚式を行いました。彼女は「キャロリーナ・ヘレラ」のカシミヤニット、ショートパンツ、チュールスカートを組み合わせた3ピースの衣装で、新しい花嫁スタイルを提案しました。
女優のキーラ・ナイトレイもミニマルな生活を好み、質素な結婚式を選んだセレブの一人です。このように、自分らしさを大切にしながらも洗練された地味婚のスタイルは、多くの花嫁にとって参考になる事例といえるでしょう。
ブライダル業界の生き残り策 ‐ 変化への対応
厳しい環境の中でも、ブライダル業界は様々な戦略で生き残りを図っています。
1. 差別化戦略の重要性
一部の式場は、ユニークな演出や個性的なサービスを提供することで他との違いを明確にしています。例えば、フォトウェディングに特化したプランや、少人数婚向けの特別プランなど、新たなニーズに対応する試みが進んでいます。
2. サービスの多様化
結婚式場の一部は、ブライダル事業以外にも収益源を拡大する動きを見せています。レストラン経営やイベントスペースの貸し出しを行うことで、収益の柱を増やす戦略を取る企業も増えています。
3. 顧客満足度の向上
生き残るためには、顧客満足度の向上が不可欠です。価格競争に巻き込まれるのではなく、質の高いサービスを提供し、口コミやリピーターの獲得を目指す式場が成功を収める可能性が高いとされています。
レストランウェディングのような新しいスタイルの登場や、個性を重視する「自分たちらしさ」を大切にする流れの中で、柔軟な提案ができるウェディングプランナーの役割はより重要になっています。
日本のカップルの実態 ‐ 出会いから結婚まで
ブライダル産業の未来を考える上で、現代の日本のカップルの実態を知ることも重要です。リクルートブライダル総研のアンケート調査(2015年版)によると、カップルの出会いのきっかけは「友人知人、兄弟姉妹を通じた紹介」が最も多く29.3%、次いで「職場や仕事での出逢い」が28.2%となっています。
結婚までに付き合った期間は平均3.6年で、1〜2年未満が最も多く23.3%、2〜3年未満が22.8%と続きます。全体として、数年の交際期間を経て結婚に至るケースが一般的なようです。
こうした実態を踏まえ、出会いから結婚までの道のりを考慮したブライダルサービスの提供が求められています。
今後の展望 ‐ ブライダル産業の行方
コロナ禍が落ち着き、ブライダル市場には一部活気が戻ってきたものの、少子化による結婚適齢期人口の減少や未婚率の上昇、婚姻数の減少により、ブライダル産業を取り巻く環境は引き続き厳しさを増しています。
さらに、コロナ禍以前から広がっていた「ジミ婚」「ナシ婚」が一般的になり、業界は変革を迫られています。マーケットは縮小しても結婚は人生の一大イベントであることに変わりなく、底堅いニーズは見込まれます。そのため、ユーザーに選ばれる魅力的なプランや設備は欠かせません。
今後、他社との差別化を図るサービス、価格の見直し、そして顧客の満足度が生き残りのカギになるでしょう。「地味婚」「ナシ婚」の流れは、単なる節約志向ではなく、「自分たちらしさ」を重視する現代カップルの価値観を反映したものでもあります。ブライダル業界がこの価値観の変化にどう対応していくかが、業界の将来を左右するといっても過言ではないでしょう。
まとめ ‐ 変わりゆく結婚式の形
ブライダル産業は今、大きな転換期を迎えています。「ジミ婚」「ナシ婚」の増加、婚姻数の減少、業界の競争激化と倒産の増加など、従来のビジネスモデルでは生き残りが難しい状況です。
しかし、こうした変化は単なる危機ではなく、新たな可能性を秘めています。カップルの多様な価値観に寄り添い、「自分たちらしい結婚式」を提案できる企業や、結婚式以外の収益源を確保する柔軟な経営戦略を持つ企業が、今後の業界をリードしていくことでしょう。
結婚式は形を変えても、人生の節目を祝う大切な儀式として存在し続けるでしょう。ブライダル産業には、変化する時代と価値観に柔軟に対応しながら、カップルにとって意義ある瞬間を創出する役割が、これからも求められています。