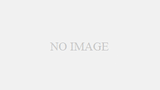バイオ燃料というと「最近の環境に優しい新技術」というイメージをお持ちの方も多いのではないでしょうか。しかし実は、バイオ燃料の歴史は自動車の誕生とともに始まっており、100年以上の歴史があるのです。今回は、あまり知られていないバイオ燃料にまつわる意外なエピソードから最新トレンドまで、クルマ好きならではの視点でご紹介します。
意外と知らない!自動車の始まりはバイオ燃料だった
自動車の歴史を語るとき、必ず名前が出てくるヘンリー・フォード。彼が約1世紀前に開発した伝説的な第1号T型フォードは、実はガソリンではなく「アルコール」を燃料として走っていたのをご存知でしょうか?同様に、ディーゼルエンジンの発明者として知られるルドルフ・ディーゼル氏が最初に製作したエンジンは、ピーナッツ油を燃料としていました。
さらに興味深いのは、1900年のパリ万博でディーゼル氏が自らのエンジンを披露した際、ピーナッツ油を燃料として選んだ理由です。当時はガソリンが希少で高価だったため、「比較的土地を選ばず栽培でき、地産地消が可能である」ピーナッツ油を選択したというのです。今でいうSDGsの考え方に近いものがあったことは驚きですね。
しかし、その後石油の精製技術が発達し、植物由来の燃料よりもエネルギー効率が高く、製造コストも安い石油燃料が普及していきました。こうして自動車の燃料は石油に統一されていったのです。
日本の戦時中、実はサツマイモから燃料を作っていた!
意外に知られていないのが、日本の第二次世界大戦末期の取り組みです。マリアナ諸島の陥落で東南アジアからの石油供給が途絶え、軍艦や戦闘機の燃料確保が国家的課題となっていました。そこで海軍省は「新燃料戦備」計画を立案し、国内で手に入るサツマイモからエタノールを製造する計画を進めたのです。
さらに興味深いのは、この計画では全国の日本酒蔵元を燃料用エタノール工場に転換する予定だったということ。1945年10月から本格生産に入る計画でしたが、8月に戦争が終結したため実現しませんでした。もし実現していれば、日本の酒造りの風景はまったく異なるものになっていたかもしれません。
また、満州向けの戦車には大豆由来のバイオディーゼル燃料の使用が検討され、1935年には池貝鉄工所が大豆油を燃料にしたディーゼル車で三本木から青森間を走破することに成功していたというエピソードもあります。
オイルショックが蘇らせたバイオ燃料への関心
バイオ燃料が再び日の目を見るきっかけとなったのは、1973年の第1次石油ショックでした。米国をはじめとする石油輸入国はエタノールを見直し、ガソリンに混合して供給不足を補い始めたのです1。特にブラジルでは、エネルギー自給率を高める目的で1975年に「国家アルコール計画(PROALCOOL)」を策定し、ガソリンに20%のエタノールを混合する取り組みが始まりました。
この計画は大きな成功を収め、1986年にはブラジルでの販売車両の92%がE100(100%エタノール燃料)車となるまでに至りました。現在でもブラジルの新車市場の約90%がFFV(フレックス燃料車)を占めており、バイオ燃料大国としての地位を確立しています。
ミドリムシがバスを走らせる!?最新バイオ燃料技術
近年特に注目を集めているのが、藻類の一種「ミドリムシ」を利用したバイオディーゼル燃料です。株式会社ユーグレナといすゞ自動車が共同開発した「DeuSEL®(デューゼル)」は、ミドリムシから抽出した油脂を100%使用した次世代バイオディーゼル燃料です。
実は従来のバイオディーゼル燃料の主原料である使用済み食用油は、世界的な需要拡大に伴い価格高騰が問題となっていました。そこで、食用油の原材料よりも油脂生産効率が高いミドリムシに着目したのです。
2023年1月には、このミドリムシ由来のバイオ燃料「サステオ」を使った都営バスが試験運行されました。JR高田馬場駅と上野公園を結ぶルートなど7路線の58台で1カ月程度使用されたこのバスには、持続可能な開発目標(SDGs)を啓発するサンリオのキャラクター「ハローキティ」がデザインされていたとのこと。環境技術とかわいいキャラクターの意外な組み合わせが話題を呼びました。
マツダが挑む!バイオディーゼルでレース完走
もうひとつ注目すべき取り組みとして、マツダの挑戦があります。マツダは「サステオ」を利用した実証実験を2020年から実施し、2023年のスーパー耐久シリーズ第2戦では、100%の「サステオ」を使用した車両で24時間レースを完走するという快挙を達成しました。
この挑戦は単なるPRに留まらず、次世代バイオ燃料の実用性を証明する重要な一歩でした。マツダの搭載エンジンSKYACTIV-D 2.2は、化石由来の軽油ではなく100%バイオ燃料でも十分な性能を発揮することが実証されたのです。
バイオ燃料の課題と未来
バイオ燃料の最大の魅力は、燃料の燃焼段階ではCO2を排出しますが、原料であるバイオマスが成長過程で光合成によって同量のCO2を吸収するため、カーボンニュートラルの実現に貢献できる点です。
しかし課題もあります。現状では製造コストが化石燃料と比較して非常に高く、例えば都営バスで使用されたバイオ燃料は軽油の約70倍という高額なコストがかかっています。また、食料と競合する可能性がある点も問題として指摘されていま。
そのため日本では、食物との競合を避けるため、廃食用油の利用やミドリムシなどの新原料の開発が進められています。特に注目されているのが「次世代バイオ燃料」と呼ばれる、食料と競合しないバイオマス原料で作られた炭化水素系のバイオ燃料です。
歴史は繰り返す?自動車燃料の未来
バイオ燃料の歴史を振り返ると、実は自動車の発明当初はバイオ燃料が主流だったものの、石油の利便性に押されて衰退し、石油ショックを契機に再び注目され、環境問題を背景に新たな発展を遂げるという波があることがわかります。
トヨタ自動車は2018年、ガソリンにエタノールを混合して走行できるフレックス燃料車に、世界で初めてハイブリッドシステムを搭載した試作車を公開しました。これはバイオ燃料とハイブリッド技術を組み合わせることで、CO2排出量をさらに削減する取り組みです。
歴史の皮肉なことに、石油に押されて忘れられていたバイオ燃料が、今また自動車の未来を支える重要な技術として注目されています。自動車の始まりに使われていた技術が、持続可能な未来を作るカギになるというのは、なんとも感慨深いものがありますね。
バイオ燃料は単なるトレンドではなく、私たちのモビリティの歴史と未来を結ぶ重要な架け橋なのかもしれません。先人たちが夢見た「地産地消」の燃料社会が、最先端技術によって実現する日も、そう遠くないのかもしれませんね。