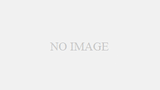60年の歴史に幕、変わりゆく女子教育の現場から
京都の地で60年以上にわたり女子教育の灯を守り続けてきた京都ノートルダム女子大学が、2026年度以降の学生募集を停止することを発表しました。2025年4月22日の学校法人ノートルダム女学院の理事会で決定されたこの措置は、現在の学生が卒業する2029年3月をもって大学院を含めた完全閉学へと至る見通しです。北山の緑豊かなキャンパスに集う学生たちの姿は、あと4年ほどで歴史の一コマとなります。今回は、この決断に至る背景や関係者の声、そして日本の高等教育機関が直面する厳しい現実について探ってみたいと思います。
「英語のノートルダム」として歩んだ60年の軌跡
「人が変われば世界も変わる」――この言葉を掲げ、京都ノートルダム女子大学は1961年に創立されました。創立母体であるノートルダム教育修道女会の理念のもと、「徳と知」をモットーとした全人教育を通じて女性のエンパワメントに力を注いできました。
キャンパスに一歩足を踏み入れると、落ち着いた雰囲気と国際色豊かな環境が広がります。「英語のノートルダム」として認知され、定評ある英語教育とカトリック精神を基盤とした国際教育を特色としてきたこの大学は、90年代初頭からは先進的なIT環境も整備し、情報教育にも力を入れてきました。
現在は国際言語文化学部、現代人間学部の2学部に加え、女性キャリアデザイン学環、社会情報学環の2学環、さらに大学院には人間文化研究科と心理学研究科を設置。約800名の学生が学んでいます。
募集停止の裏にある厳しい現実
では、なぜこのような歴史ある女子大学が募集停止という厳しい決断に至ったのでしょうか。
最大の要因は、入学者数の定員割れが続いていることです。2024年度は定員330人に対して186人(56%)の入学にとどまり、さらに2025年度は169人(51%)と減少傾向に歯止めがかからない状況でした。
ある教職員は匿名を条件に「2021年度あたりから危機感は強まっていました」と明かします。「オープンキャンパスへの参加者は一定数いても、実際の出願、そして入学に至る数が年々減少していた。コロナ禍の影響もありましたが、それ以上に少子化と大学間競争の激化が本学を直撃したのです」。
実はこの現象、決して京都ノートルダム女子大学だけの問題ではありません。日本私立学校振興・共済事業団の調査によれば、2023年度、私立大学の半数以上が定員割れの状態に陥っていることが明らかになっています。18歳人口の減少に加え、定員厳格化の緩和といった制度変更も大学経営に大きな影響を与えているのです。
学生たちの心の声―突然の発表に戸惑いと不安
「朝、大学のポータルサイトに通知が来て驚きました」と語るのは、現代人間学部2年生の佐藤さん(仮名)です。「友達とLINEで『どういうこと?』と連絡し合いました。急すぎて受け入れられない気持ちです」。
在学生や卒業生のSNSには動揺の声が広がっています。「母校がなくなるなんて」「これからどうなるの?」と不安を訴える声がある一方で、「最後まで誇りを持って学びたい」という前向きなコメントも見られます。
京都ノートルダム女子大学では「在学生が卒業するまでの教育や就職支援は丁寧に行う」と約束していますが、学生たちの心配を完全に払拭するのは難しい状況です。
ある卒業生はこう語ります。「私が学生だった頃も少子化は話題でしたが、まさか母校がなくなるとは思いませんでした。少人数制で先生との距離が近く、一人ひとりを大切にする教育が魅力だっただけに残念です」。
小学校・中学校・高校は存続、女子教育の灯は消えず
注目すべきは、学校法人ノートルダム女学院が運営する小学校、中学校、高校は存続するという点です。女子教育の根幹を守りながら、高等教育機関のみを閉じるという選択は、限られた資源をどこに集中させるかという学校法人の苦渋の決断でしょう。
「小中高の教育は伝統を守りながらも時代に合わせて変化させていく必要があります」と、学院関係者は語ります。「大学の閉学は痛みを伴う決断でしたが、学院全体の持続可能性を考えた結果です」。
女子大学の存在意義と現代社会における挑戦
女子大学は近年、その存在意義について問われることが増えています。共学化の流れが進む中、あえて女子のみの教育環境を維持する理由は何なのか。
興味深いのは、近隣の京都女子大学が2021年に発表した宣言広告です。「意思決定の場に、もっと女性を!」というタイトルのもと、「社会の中で自ら手をあげ、意思決定権を持ち、その意思を実現へと導く女性を育てる」ことを約束しています。
この宣言には、日本のジェンダー・ギャップ指数が153カ国中121位(2020年時点)という厳しい現実が背景にあります。学長の竹安栄子氏は「女子しかいないからこそ、忖度なく真正面からジェンダー教育もできる。女子大学だからこそ、真の女性リーダーの育成ができる」と主張しています。
京都ノートルダム女子大学の中村久美学長も、「わたしらしく、誇らしく」成長していく学生を、小規模女子大学のメリットを活かし、教職員全員で温かく見守る教育を大切にしてきました。女子大学ならではの教育環境の価値を信じてきたからこそ、今回の決断は関係者にとって痛恨の極みでしょう。
最後の4年間―どのように「幕」を下ろすのか
今後、京都ノートルダム女子大学はどのように最後の4年間を過ごすのでしょうか。
大学は公式ホームページで「在学生が卒業するまでの教育や就職支援は丁寧に行う」と約束しています。また、学生や保護者向けの説明会も予定されているとのことです。
教育現場の最前線からは「今いる学生たちが誇りを持って卒業できるよう、最後まで質の高い教育を提供したい」という声が聞こえてきます。キャンパスには複雑な思いが渦巻いていますが、残された時間をどう過ごすかが問われています。
私立大学の未来図―京都ノートルダム女子大学からの警鐘
京都ノートルダム女子大学の募集停止は、日本の高等教育機関、特に私立大学の未来に対する警鐘と受け止めるべきでしょう。京都府内には34の4年制大学があり、うち私立は27校。公立を含めて府内4年制大学が募集停止を行うのは初めてのことだと報じられています。
今回の件は氷山の一角に過ぎないという見方もあります。2023年3月以降、恵泉女学園大学(東京都)、神戸海星女学院大学(兵庫県)、上智短期大学(神奈川県)など、次々と募集停止を発表する私立大学・短期大学が現れました。
大学関係者の間では「次はどこが…」という緊張感が広がっています。教育の質を保ちながら経営を維持するという難題に、各大学は知恵を絞っているのです。
変わりゆく大学の姿、変わらぬ教育の本質
京都ノートルダム女子大学の募集停止という事実は、高等教育機関の形が時代とともに変わっていくことを示しています。しかし、同時に「人が変われば世界も変わる」という創立理念は、形を変えながらも受け継がれていくのではないでしょうか。
最後に、京都ノートルダム女子大学のある卒業生の言葉を紹介します。「私たち卒業生は、大学からいただいた学びを社会で生かし続けています。校舎がなくなっても、教育の精神は私たち一人ひとりの中に生き続けるのです」。
京都の北山の地で60年以上にわたり輝き続けた女子教育の灯。その光は、形を変えながらも、これからも社会の中で生き続けていくことでしょう。