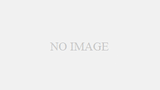柳田邦男『「死後生」を生きる 人生は死では終わらない』──その深層と裏話
ノンフィクション作家・柳田邦男が88歳で世に問うた『「死後生」を生きる 人生は死では終わらない』(文藝春秋)。本書は、半世紀以上にわたり「生と死」を追い続けてきた柳田氏の集大成的アンソロジーです。単なる人生論や死生観の書にとどまらず、彼自身の壮絶な家族体験、現場取材のリアルなエピソード、そして“死後生”という新たな希望の概念を提唱する一冊。その背景や裏話、エピソードを交え、話題の理由を深掘りします。
「死後生」とは何か?──柳田邦男の新しい死生観
柳田氏が本書で提唱する「死後生」とは、肉体が滅びても、その人の思いや愛、言葉や行為が、遺された人の心の中で生き続けるという考え方です。これは、単なる“死後の世界”や“魂の不滅”とは異なり、現実に生きている人々の精神や行動に、亡き人の存在が影響を与え続ける“精神的な命の継承”を意味します。
柳田氏は、人生の最終章を自分でどう書くか、そして「さよならなき別れ」からどう生きなおすかを問いかけます。彼自身が多くの死別体験を重ねてきたからこそ、説得力を持って語れるテーマです。
裏話1:次男の死が生んだ“死後生”の原点
柳田氏の死生観の原点には、1993年に次男を自死で亡くしたという壮絶な家族体験があります。その時の葛藤と苦悩を綴った著書『犠牲 わが息子・脳死の11日』は、臓器移植や脳死問題にも深く切り込んだ名著として知られています。次男は生前、骨髄移植のドナー登録をしていたことから、柳田氏はその意志を汲み、腎移植によって2人の命を救いました。
この体験を通じて、「人は2度死ぬ。1度目は肉体の死、2度目は記憶から消えたとき」という思いに至り、亡き人の存在を語り継ぐことの大切さを痛感したそうです。本書の「死後生」も、まさにこの実体験が根底にあります。
裏話2:ノンフィクション作家としての矜持と現場主義
柳田氏は、NHK記者時代から“現場主義”を貫いてきました。取材で直接聞いた生の声や表情は、今も鮮明に記憶に残ると語っています。本書でも、医療現場や看取りの現場で出会った数々のエピソードが紹介されており、「現場でしか得られない実感」が文章に力を与えています。
また、米寿を迎えてもなお、2時間の講演を30分以上オーバーしてしまうほどの情熱と記憶力を保ち続けているのも、現場での経験が彼の原動力となっている証でしょう。
裏話3:家族の苦難と再生
柳田家は、決して順風満帆な家族ではありませんでした。妻は次男の幼少期の事故をきっかけに神経症となり、長男もウイルス性脳炎で生死をさまよった経験があります。家族の苦難と向き合いながら、柳田氏は“生きること”と“看取ること”の意味を問い続けてきました。
このような家族の歴史が、柳田氏の死生観や「死後生」という概念をより深く、リアルなものにしています。
裏話4:コロナ禍での看取りの意味
近年、柳田氏が強調するのが「看取りの大切さ」です。コロナ禍で家族が最期の別れをできない事例が増えたことで、看取りの機会がいかに大きな意味を持つかを再認識したといいます。自身の母親を看取った際、寝たきりの母が声をかけると涙を流したという体験も、看取りの重要性を語る原体験となっています。
「人生の最終章」を自分で書く──読者へのメッセージ
柳田氏は「死は人生の最終章。その章をどう書くかは自分次第」と繰り返し語ります。納得できる死を迎えるためには、医学的な対応だけでなく、精神的な準備や人生の物語の“締めくくり”が重要だと説いています。
また、「死後生」は、遺された人の人生を豊かに膨らませるものであり、亡き人の思いを受け継いで生き直す力になるとしています。
エピソード:現場で出会った「死後生」の証
本書には、著名人や一般の人々の「死後生」にまつわるエピソードが数多く紹介されています。例えば、日野原重明氏や金子兜太氏といった先人たちの“精神的な命”が、今も多くの人の心の中で生き続けていること。また、亡き人との“日常会話”を続ける15人の証言など、読者の心に響く実話が満載です。
トピック:大人こそ絵本を──柳田流“生き直し”のすすめ
柳田氏は「大人こそ絵本を読もう」とも呼びかけています。絵本は、死や別れをやさしく、しかし深く考えさせてくれるツールであり、グリーフケア(悲嘆ケア)の一助にもなるといいます。
まとめ:なぜ今「死後生」が話題なのか
現代は、医療の進歩や高齢化により、死生観が大きく変わりつつあります。延命治療や緩和ケアなどの選択肢が増えた一方で、「納得できる死」とは何かを自ら考え、準備する時代になりました。
柳田邦男『「死後生」を生きる』は、単なる“死を考える本”ではなく、死を通して「どう生きるか」「何を遺すか」を問いかける“生き直し”の書です。家族の苦難や実体験、現場での取材を通じて生まれた“死後生”という希望の概念は、今を生きる多くの人に勇気とヒントを与えてくれるでしょう。
人は死によって肉体は失くなっても、その人の思いや愛や言葉や行為は、遺された者たちの心の中でずっと生き続ける──柳田邦男『「死後生」を生きる』
今こそ、多くの人に読んでほしい一冊です。