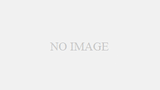「恩送り(おんおくり)」という言葉、最近SNSやビジネス書などで目にする機会が増えています。「受けた恩を直接返すのではなく、別の誰かに送る」という意味で使われることが多いですが、実はこの言葉、歴史的にも現代的にも意外なエピソードや変遷があるのをご存じでしょうか?
「恩送り」の本来の意味と現代的な誤解
現代では「恩送り=受けた恩を別の人に送る」という意味が定着していますが、実はこの使い方は本来の意味とは異なります。最大の国語辞典『日本国語大辞典』や古語辞典によると、「恩送り」「恩を送る」はもともと「恩返し」と同じ意味、つまり“受けた恩に報いる”という意味で使われていました。
江戸時代の歌舞伎『菅原伝授手習鑑』にも「恩送り」が登場し、当時の庶民にも広く知られていた可能性があります。しかし、時代が下るにつれて「恩返し」という言葉が主流となり、「恩送り」は一度忘れられた言葉となっていきました。
言葉の変遷と“恩”の意識の変化
「恩送り」は16世紀ごろに生まれた言葉で、それ以前は「恩に報いる」「恩に報ずる」という表現が一般的でした。江戸時代以降、「恩返し」という言葉が登場し、現代では「恩返し」が当たり前の表現に。
この言葉の変遷は、日本人の“恩”に対する意識の変化を映し出しています。かつては「恩は報いるもの」だったのが、「恩は送るもの」になり、やがて「恩は返すもの」へと変化していったのです。
現代に蘇った「恩送り」ブームの裏話
現代で「恩送り」が再び注目されるきっかけとなったのは、作家・井上ひさし氏のエッセイや、海外の“Pay it forward”運動の影響が大きいとされています。SNSやビジネスの現場で「恩送り」が使われるようになった背景には、「恩返し」だけでは循環しきれない社会の複雑さや、直接返せない恩への戸惑いがあったのかもしれません。
実際、「恩送り」を実践した人のエピソードとしては――
- あるカフェで「次の人のコーヒー代を払っておいて」と伝えたら、見知らぬ誰かがその恩を受け取り、さらに別の人へと“恩”がリレーされていった。
- 会社で先輩から受けた親切を、後輩に同じように返すことで、職場全体の雰囲気が良くなった。
など、現代社会ならではの“恩のリレー”が各地で生まれています。
「恩送り」の今後とあなたへのメッセージ
「恩送り」は、もともと“恩返し”と同じ意味だった言葉が、時代を経て“恩のリレー”という新しい価値観をまとって蘇ったもの。現代の人々が「恩は返すものなのか?」と疑問を持ち始めたことが、再評価のきっかけになったとも言われています。
あなたも、誰かから受けた親切や支援を、直接その人に返せなくても、別の誰かに“送る”ことで、社会全体に温かい循環を生み出すことができるかもしれません。
「恩送り」は、時代を超えて人と人をつなぐ、日本らしい美しい文化のひとつ。ぜひ、あなたの日常にも取り入れてみてはいかがでしょうか?